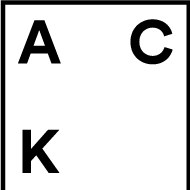「生誕100年 元永定正のドキュメンテーション -Riding on a time machine-」
元永定正の生誕100年を記念した本展では、絵画作品、スケッチ、写真、模型、展覧会記録など、あふれんばかりの痕跡から元永の人生を振り返ります。元永定正とは何者か。残された資料から人物像に迫ります。(HPより)
2022年9月10日(土) ―2022年10月10日(月)
夏季休廊のお知らせ/Closed for Summer Holiday
下記の期間を夏季休廊とさせていただきます。
Yoshiaki Inoue Gallery will be closed for summer holiday.
2022年8月12日 (金) – 8月21日 (日)
August 12 (fri) – August 21 (sun), 2022
北川宏人作品展示情報/金沢21世紀美術館
北川宏人の作品が金沢21世紀美術館と国立工芸館の所蔵作品によるコラボレーション展「ひとがた」をめぐる造形に出品されます。
2022年7月23日(土) ―2022年9月11日(日)
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa Exhibition Information(ENG)
詫摩昭人「逃走の線/ Lines of Flight- Color」
July. 15 Fri - Aug. 10 Wed, 2022

ジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze、1925-1995)が唱えた「逃走の線」から着想を得て、油彩で描いた画面が乾かないうちに、横幅2mの刷毛を一気に上端から下端へ走らせる最後の瞬間で作品を仕上げる詫摩昭人の新作展。
今展ではカラーシリーズの初発表になります。
It has been almost 18 years since I began creating “Lines of Flight,” an oil painting done with one stroke with a brush two meters across. I tried many times in the past to create works in color, but I have never been able to produce anything satisfactory. But I decided to hold my first solo exhibition featuring color works, as I believe that for the first time I have something to show to you.
The concept of weaving between dichotomies is a theme that runs through the foundation of my work. I created my color works around two axes: “colored and achromatic,” and “false and real images”. The latter was inspired by landscape reflected on the surface of water.
With the pandemic beginning in 2020, and tensions in Ukraine cropping up in 2022, the world of today is one full of turbulence. But there is still beauty from the coming together of things, of things unfragmented. I hope you are able to enjoy the exhibit.
June, 2022 Akihito Takuma
⽩⿊の作品は、⽩と⿊という、時には⼆項対⽴とも⾔える軸を⽣み出しやすかったので、これまで⼀貫して作っていました。過去にもカラー作品を試したことは数多くあります。その時は補⾊で作ったりもしましたが、どこかぐちゃぐちゃとなり対⽴軸を作ることができず、今ひとつしっくりいかず、ほとんど発表することはありませんでした。しかし、今回やっとで、有彩⾊と無彩⾊の対⽐の作品を⽣み出せたと感じ、発表しても良い気持ちになりました。
ただ、カラー作品を作ろうとしたきっかけは、⽔⾯に映る⾵景が、⽔に映り、とけこんでいて、実像と虚像が⼊り混じった様⼦を魅⼒的に思い、そこからヒントを得た部分もあります。なので、現在のカラー作品には、⼤きく⼆つのひらめきがあります。
詫摩昭人
Art Osaka 2022
この度第20回目となりますArt Osaka 2022に参加致します。
20回目の記念として通常のフェア会場とは別の場所でExpanded Sectionとして大型スペースでの展示もあり、青野セクウォイア/Sequoyah Aonoのインスタレーションを行います。
大阪市中央公会堂で行われるGalleries Sectionでは5名の作家を紹介致します。
artist: 北川宏人/Hiroto Kitagawa、平 久弥/Hisaya Taira、岡本啓/Akira Okamoto、内田ユイ/Yui Uchida、松谷武判/Takesada Matsutani
ユアサエボシ参加のグループ展 7/1-8/12
ソウルのNobllesse Collectionで行われます4作家によるグループ展<Alter Ego>に参加しています。韓国の若手作家の中に入って大きな注目を集めています。
Artist
Kang Mok(1988-), Paek Yunzo(1980-), Qwaya(1991-), Yuasa Ebosi(1983-)
”Alter Ego”

130.3×162cm/Acrylic on canvas/2016

91×72.7cm/Acrylic on canvas/2015

72.7×60.6-cm/Acrylic on canvas/2013
DIE GROSSE KUNST AUSSTELLUNG NRW
井上廣子がデュッセルドルフのクンストパラスト美術館で行われる、アーティストによるアーティストのためのドイツ国内最大で100年以上の伝統を誇る展覧会「DIE GROSSE 2022」に参加します。
Hiroko Inoue is participating in the group exhibition. “DIE GROSSE Kunstausstellung” is the largest exhibition in Germany organised by artists.
“DIE GROSSE Kunstausstellung”
Museum Kunst Palast 6/12 – 7/17
https://www.kunstpalast.de/die-grosse-2022-en



PLAY
April 11 Mon-April 30 Sat, 2022

内田 ユイ / Yui Uchida
原口 みなみ / Minami Haraguchi
ダニエル・ヌニェス / Daniel Nuñez
English follows Japanese
内田ユイ、原口みなみ、ダニエル・ヌニェスの若手作家3人によるグループ展「PLAY」を開催いたします。
内田ユイは、山梨県出身、東京都在住のアーティスト。内田はアニメーションの製作過程において用いられるセル画の技術を応用して制作を行います。現代社会において新しい技術が日々生み出されセル画技術がデジタルに移行する中で、内田はこのセル画を用いることにより絵画に運動を与えることに成功しました。透明のシートに描かれるイメージは、どこか懐かしさを感じさせ私たちの記憶の間で歩き出し、それぞれのストーリーを生み出させます。今やアニメーションの制作の技術の向上により失われつつもあるセル画の技術を使用することと、描かれたイメージが結びつくのも内田の仕掛けたトリックの一つであると言えるでしょう。
原口みなみは、大阪府出身、2016年に京都市立芸術大学院修士課程を修了し、現在も大阪で活動するアーティスト。身の回りに存在する何気ないものや風景をドローイング、コラージュ、粘土、アクリル、オイルなど様々な素材や媒体間を何度も横断し、繰り返し重ねて描きます。ある部分は突出したり、ある部分は失われたりして、素材として用いられたイメージは原型を失っていきます。それは個人の記憶や思い出が、時とともに変容していく様を表現しているようで、私たち鑑賞者は最後に残ったキャンバスから原口が見て感じて経験してきたものだけでなく、私たち自身の記憶や思い出をも想起させます。
ダニエル・ヌニェスは、1988年にスペインのマドリードに生まれ、Higher School of Professional Drawing (ESDIP)を卒業し、現在もマドリードにスタジオを構えるアーティスト。ヌニェスは、自身を取り巻く様々なシンボルを彼自身の世界観に置き換え、独自のタッチで表現します。靴、植物、電話など私たちの身の回りに存在する何気ない日常のアイテムは、ヌニェスのキャンバスを通して無視できないものへと生まれ変わり、魔法のように物理的な存在感を獲得します。
本展は、遊び心の中の誠実さをテーマに、これからを担う若き才能のみずみずしい感性や未来を創造する力強さと可能性を紐解きます。
We, Yoshiaki Inoue Gallery are pleased to present the group exhibition “PLAY” by three young artists, Yui Uchida, Minami Haraguchi, and Daniel Nuñez.
Yui Uchida is an artist born in Yamanashi and currently based in Tokyo. She creates works by applying celluloid techniques; anime-cels, used in the animation production process. While new technologies are being created every day in today’s society and the use of anime-cels are shifting to digital technology, Uchida applies and utilizes this traditional celluloid technique to give movement to her paintings. The images depicted on the transparent sheets evoke a sense of nostalgia, walk among our memories, and create their own stories. Uchida links the fragility of these vanishing celluloid techniques with the images themselves drawn on these vulnerable transparent sheets.
Minami Haraguchi is an artist born and based in Osaka and completed her MFA at Kyoto City University of Arts in 2016. Haraguchi paints ordinary objects and landscapes that exist around her; repeatedly crossing between various materials and mediums such as drawing, collage, clay, acrylic, and oil. Some parts protrude, while some parts are lost and the images used as inspiration lose their original forms as our personal memories transform over time. The canvas reminds not only of what the artist has seen, felt, and experienced, but also evokes our own memories.
Daniel Nuñez was born in Madrid, Spain in 1988, graduated from Higher School of Professional Drawing (ESDIP), and is still based in Madrid where the artist has a studio. Nuñez translates the various symbols that surround him into his own worldview and expresses them with his unique painting technique. Common everyday items that exist around us, such as shoes, plants, and telephones are transformed in Nunez’s canvas into something non-negligible, magically acquiring a physical presence.
With the theme of sincerity in playfulness, this exhibition, “PLAY” unravels the raw sensitivity of emerging talents and their strength as well as their potential to create a new future.
Art Fair TOKYO 2022
March 11 Fri – March 13 Sun, 2022 (preview: March 10)
artist
Hiroto KITAGAWA/北川宏人
Toshio SHIBATA/柴田敏雄
Akihito TAKUMA/詫摩昭人
U-die/ユーダイ
Ebosi YUASA/ユアサエボシ
Booth:S023
venue:東京国際フォーラム ホールE /Tokyo International Forum Hall E
https://artfairtokyo.com/
北川宏人/Hiroto Kitagawa 「Space & Ceramic」
 北川宏人(1967年-)はモデリングの状態から乾燥過程で内部の粘土を掻き出すことで空洞をつくり、原型をそのまま焼成するという特殊な手法で「時代を切り取る」彫刻作品を作り続けてきました。やわらかい粘土で細身の立像を作り上げるという困難な手法で等身大の制作を続けてきた北川が、コロナ禍の与えられた時間の中でこれまでの経緯を振り返り、土や釉薬についての課題に取り組みながら、新たな挑戦として初めて等身大を超える2メートル級の制作に取り組みました。作品は世の中を宇宙空間というスケールに置き換えそれを守る戦士のイメージです。
北川宏人(1967年-)はモデリングの状態から乾燥過程で内部の粘土を掻き出すことで空洞をつくり、原型をそのまま焼成するという特殊な手法で「時代を切り取る」彫刻作品を作り続けてきました。やわらかい粘土で細身の立像を作り上げるという困難な手法で等身大の制作を続けてきた北川が、コロナ禍の与えられた時間の中でこれまでの経緯を振り返り、土や釉薬についての課題に取り組みながら、新たな挑戦として初めて等身大を超える2メートル級の制作に取り組みました。作品は世の中を宇宙空間というスケールに置き換えそれを守る戦士のイメージです。
今展ではこの大作を中心にSpace&Ceramicというテーマに沿ってこれまでの作品を含めたインスタレーションでご紹介致します。
Memory of the Beach
Nov.25 wed- Dec. 20 Mon, 2021
Marc DESGRANDCHAMPS/マーク・デグランシャン(French)
Yang-Tsung FAN/范揚宗 (Taiwan)
Katsura FUNAKOSHI/舟越桂
Akihito TAKUMA/詫摩昭人
Hiroko INOUE/井上廣子
Art Collaboration Kyoto
November 5 Fri, – 7 Sun, 2021
Participating artists : Booth A06
田原桂一/Keiichi TAHARA (Japan)
松谷武判/Takesada MATSUTANI (Japan)
北川宏人/Hiroto KITAGAWA (Japan)
郭志宏/KUO Chih-Hung (Taiwan)
范揚宗/Yang-Tsung Fan (Taiwan)
Marc DESGRANDCHAMPS (France)
Kai SCHIEMENZ (Germany)
Guest GalleryにAKI Gallery(台湾)とGalerie EIGEN+ART(ドイツ)を迎え共同での展示となります。
詫摩昭人 「逃走の線/ Lines of Flight-Skyscraper Ⅱ」

Sep. 24 Fri - Oct. 20 Wed, 2021
ジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze、1925-1995)が唱えた「逃走の線」から着想を得て、油彩で描いた画面が乾かないうちに、横幅2mの刷毛を一気に上端から下端へ走らせる最後の瞬間で作品を仕上げる詫摩昭人の新作展。
今展は、ここ数年間取り組んでいるテーマ「Skyscraper(摩天楼)」の都市の範囲も広げさらに発展させています。
修正の利かない制作工程で一度限りの美を追求する作品群をご高覧下さい。
80号3点を連結させた大作(145.5 x 336cm)を中心とした展示となります。
中辻悦子展 ーWHO IS THIS? あなたは、誰(だあ)れー
宝塚市立文化芸術センターのメインギャラリーで中辻悦子の個展が開催されております。(9/4-10/11)
中辻悦子の50年以上にわたり「ひとのかたち」をテーマにしながら決して自己模倣に陥らず創作活動を続けています。
今展ではその中から、活動初期のオブジェやそこから発展していったインスタレーション、大作キャンバス作品の近作の数々、木製オブジェのインスタレーション、ブラティスラヴァ世界絵本原画展グランプリを受賞された「よるのようちえん」が動き出す映像作品など、多岐にわたる楽しさあふれる活動内容が紹介されています。
https://takarazuka-arts-center.jp/wordpress/2021/08/01/202109to10nakatsuji/

Real – 陶芸の可能性Ⅱ / Contemporary Ceramics
July 27 – August 13, 2021
 陶芸の技術や土という素材を出発点としながらも新しい表現を模索し続ける4名の作家たちをご紹介します。
陶芸の技術や土という素材を出発点としながらも新しい表現を模索し続ける4名の作家たちをご紹介します。
それぞれが抱える時代性や方向性はじつに様々であり多彩な才能の競演の場となります。
陶芸の可能性をぜひご覧下さい。
<出展作家>
秋永邦洋 Kunihiro Akinaga
北川宏人 Hiroto Kitagawa
田島弘庸 Hirotsune Tashima
桑田卓郎 Takuro Kuwata (※collection)
Art OSAKA 2021
July 18 Sat – July 20 Tue, 2021
Artist:
北川宏人/Hiroto KITAGAWA
詫摩昭人/Akihito TAKUMA
岡本啓/Akira OKAMOTO
ユアサエボシ/Ebosi YUASA
新村卓之/Takuji SHIMMURA
青野セクウォイア/ Sequoyah Aono – Face to Reality –

June 19 Sat, - July 15 Thu, 2021
青野セクウォイア(1982年イタリア生まれ)
東京で育ち、ニューヨークで彫刻を学んだ後2007年東京藝術大学大学院修了。現在、ニューヨークと日本を拠点に活動。
当ギャラリー初個展となる今展では、自身のスタジオ近辺で見かける石灯篭から発想を得た作品の発表となります。このコロナ禍にあって少しでも未来を照らしだせるものとの想いも込めた等身大作品を中心にしたインスタレーションと、木彫のミニセルフポートレートを発表致します。
Artist Statement
It has been over a decade since I started working at the part of stone factory in Sekigahara as a studio. In these few years I spend most of the time at this studio while I’m in Japan. On the way to the studio by motorbike, I often notice a stone lantern standing by the roadside. My growing up in Tokyo, it is a bit uncommon and a strange sight. Is it related to the numbers of stone factories in this area, I wonder!?
At some point in these days, I began to care about one lantern when travelling to a neighboring town. In a word, that lantern looks like a human. When that lantern happens to be at the corner of my sight, I turn around under the illusion that I come across someone. That is like human standing by the size and proportion, and I even feel a sense of its gaze through the lantern. That lantern doesn’t look so old, and I don’t want to say, “the soul dwells in the stone” or such a ghost story. It just happens to me.
The main new work in this exhibition is based from such a daily frame. Looking at the lantern like a human being, I wanted to make a sculpture combined a human and a lantern. And as I work on it, I gradually think it becomes an important meaningful motif to me. The function of “Tōrō(Japanese stone-lantern)” which leads the soul of the dead returning home by its light also seems to illuminates my road of “sculpture” I walk. Art and creation might be connected to a place, the next world. “Tōrō” doesn’t mean that it is a leading role, so to speak, but only a supporting role. For me, who spent my childhood avoiding “standing out” as much as possible, I feel the same sense of familiarity with the way the “ Tōrō” has. This time I wanted to curve the one which could play a leading role at this exhibition.
With Lantern Man centered in this exhibition, new pieces of sculptures are arranged around like installation. And among its components, numbers of “4” and “13” which are said to be ominous in Japan and Western countries are hidden. And in addition to the Western sculpture techniques I usually incorporate in, there are also parts that I refer to Asian modeling, such as Buddhist art and stone gardens. The combination of these ideas comes from my daily life. At the same time, however, under this corona pandemic Asians and Asian Americans sadly have been thrown to strict dangers in New York City, my other stronghold, all which have effect on process of my sculptures. I have a strong feeling to think over Asian and Western cultures. Now again I reconsider my identity and would like to express my role as an artist.
I’m highly grateful for visitors to the venue even in this severe condition. I hope this exhibition will lighten viewers up for the better, even slightly…
Thanks a lot to All.
関ヶ原にある石材所の一部をスタジオとして間借りするようになって、数年が経つ。近年は日本にいる時間のほとんどをこの場所で過ごしている。
スタジオの近所を車で行き来していると、よく道端に石の灯篭が立っていることに気づく。東京で育った私にとって、それは少し珍しく、奇妙な光景だった。近所に石材所が多いことも関係しているのだろうか。
そんな中でいつの頃からか、隣町に移動するときに目にする1つの灯篭が何となく気になり始めた。一言でいえば、その灯篭はまるで人間のように見えるのだ。ふとした拍子にそれが視界の隅をかすめると、誰かとすれ違ったと錯覚して振り返ってしまう。サイズやプロポーションが直立した人間に似ていて、火袋のあたりからは目線を感じる気もする。灯篭自体はそこまで古いものではなく、「石に魂が宿っている」とか、そういった怪談めいたことを言いたいわけではない。私にはたまたまそう見える、というだけの話だ。
今回の展覧会でメインとなる新作は、そんな日常の1コマに端を発している。人のような灯篭を見ているうちに、人間と灯篭を組み合わせた彫刻を作ってみたくなったのだ。そして制作を進める中で、それは次第に私にとって重要な意味を持つモチーフだと思えてきた。死者の魂を導き、弔うという灯篭の機能は、私が歩む「彫刻」という道を照らしてくれるものだとも感じられる。芸術や創造は、どこか冥界のような場所と繋がっているからかもしれない。あるいは「何かを照らすために立っている」という状態は、それ自体は主役ではなく、いわば引き立て役・脇役にすぎないということを意味している。「目立つこと」をなるべく避けて幼少期を送った自分にとって、それは少し親近感を持てる在り方だ。そんな存在が主役になる作品を作ってみたいと私は思った。
今回の展覧会では、この作品を中心としたいくつかの新作たちを、インスタレーション的に配置する。そしてその構成要素の中には、「4」や「13」といった、日本や欧米で不吉とされる数字が隠されている。また私が普段ベースとしている西洋の彫刻技術のみならず、仏教美術や石庭など、アジア的な造形を参照した部分もある。これら1つ1つの発想の組み合わせも、きっかけはあくまで日常の思いつきに過ぎない。しかし同時に、現在のコロナ禍において、私のもう1つの拠点であるニューヨークでアジア人が厳しい立場に追いやられていることなどが、制作のプロセスにも影響している。アジアや欧米の文化を見直し、今一度自分のアイデンティティを捉え直し表現したい、という思いが今の私にはある。今回の展示が、この厳しい状況下にも関わらず会場に足を運んでくれた人たちにとって、わずかでも未来を照らし出すものとなってくれたら、と思う。
青野セクウォイア
art stage OSAKA

Artist:
元永定正/Sadamasa MOTONAGA
北川宏人/Hiroto KITAGAWA
平久弥/Hisaya TAIRA
ユーダイ/U-die
ユアサエボシ/Ebosi YUASA
art stage OSAKAは「自粛・中止」となりました。(5/31)
https://artstageosaka.com/2021
※Yoshiaki Inoue Galleryではこの度出品予定でしたアーティストによるGroup showを行います。6/15まで








元永定正/Sadamasa MOTONAGA - Large and Small –
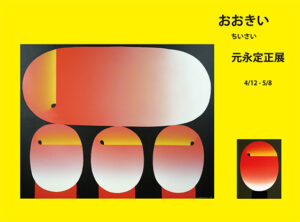
April 12 Mon - May 8 Sat, 2021
1922年三重県生まれ。1955年「具体美術協会」に参加し、退会までの16年間の全展覧会に出品。具体美術の代表的作家として、絵画、彫刻、インスタレーション、パフォーマンス、舞台美術など、実験的かつ自由で遊び心のある作品を制作されました。
また中辻悦子氏デザインによる絵本も多数発表され、子どもたちが創作世界の楽しさに触れられるような活動もされています。
そんな元永さんが亡くなられてから、早や10年。
この没後10年の節目に、元永さんの絵本「おおきい ちいさい」をイメージした作品展を開催いたします。
ぜひご高覧ください。
Art Fair TOKYO 2021
March 19 Fri – March 21Sun, 2021 (preview: March 18)
artist
北川宏人 / Hiroto KITAGAWA
元永定正 / Sadamasa MOTONAGA
中辻悦子/Etsuko NAKATSUJI
田原桂一 / Keichi Tahara
ユーダイ / U-die
Booth:G18
venue:東京国際フォーラム ホールE /Tokyo International Forum Hall E